今回の記事の結論
- わかりずらいけど活用したい!行動経済学の考え方をまとめてみました!
- ビジネスシーンだけでなく自分を知ることにもつながる。
- 「行動経済学が最強の学問である」(著:相良奈美香)より引用。
行動経済学理論まとめ表
| No | 要因 | 分類 | 理論 | 概要 |
| 1 | 認知のクセ | システム1のクセ | システム1vsシステム2 | 直感vs論理。サラダよりケーキを選ぶ不合理な選択を疲れているときにしがち。 |
| 2 | 非流暢性(ひりゅうちょうせい) | 引っ掛かりをあえて作ることで論理的思考を起動する。(引っ掛かりがない=流暢性) | ||
| 3 | メンタルアカウンティング | お金などの使い道の仕分けがされ仕分け内で利用しようとする。全体合理的判断となりにくい。 | ||
| 4 | 自責バイアス | 人は誘惑に弱いのに誘惑に弱くないと過大評価してしまうバイアス。 | ||
| 5 | 埋没コストへの恐怖 | かけた”コスト”を失うことにとらわれて楽しく新しい方を選べない。 | ||
| 6 | 機会コストへの尊重 | 埋没コストにとらわれる裏で新しいチャンスを失っているという考え。中断の意思決定軸。 | ||
| 7 | ホットハンド効果 | マイケルジョーダンがまた決めるという思い込みの期待。(定量的確率の無視) | ||
| 8 | フット・イン・ザ・ドア | 小さいお願いから始めると人は言うことを聞いてくれる。(最初から大きなお願いは不可) | ||
| 9 | 確証バイアス | 思い込んだら都合の良い情報ばかりに目が行くこと。 | ||
| 10 | 真理の錯誤効果 | 繰り返し見たり聞いたりすると信じてしまう。 | ||
| 11 | 五感のクセ | 概念メタファー | 抽象的な概念を具体的なモノで比喩して認知する枠組み。(縦長ボトル=高級感) | |
| 12 | 時間のクセ | 双曲割引モデル | 長期的に利益になるものを先延ばし、目先の価値を過大評価する。 | |
| 13 | 解釈レベル理論 | 今は現実的かつ具体的に考え、未来は抽象的に考える。 | ||
| 14 | 計画の誤謬(ごびゅう) | あらゆる計画は見積りが甘くなり失敗するという楽観的な考え方。 | ||
| 15 | 快楽適用 | 幸福度はだんだんと一定のラインに戻ってくる。 | ||
| 16 | デュレーション・ヒールスティック | かける時間が短いと価値や合理性を感じてもらいずらくなる。 | ||
| 17 | 状況 | 初頭効果 | 初めに得た情報が印象に残りやすい。 | |
| 18 | 新近効果 | 最後に得た情報が印象に残りやすい。 | ||
| 19 | 単純存在効果 | 他者がいるだけで行動影響を受ける。人がいると高いメーカーの電池を購入してしまう。 | ||
| 20 | 過剰正当化効果 | 内発的動機の取り組みに外的(金銭的)報酬など用意されるとモチベーションが低下する。 | ||
| 21 | 情報オーバーロード | 多すぎる情報は人を疲れさせ意思決定を妨げる。 | ||
| 22 | 選択オーバーロード | 多すぎる選択肢は人を疲れさせ意思決定を妨げる。(ただ少ないと集客力が弱くなる) | ||
| 23 | 選択アーキテクチャ | 事前に選択されている、商品情報の単純化、ディシジョンツリー化、選択肢10個まで決定UP。 | ||
| 24 | ナッジ理論 | ちょっとしたきっかけを与え、本人が無意識のうちに選択を誘導すること。 | ||
| 25 | プライミング効果 | あらかじめ受けた刺激(カレー匂い)によりその後の判断や行動が影響を受ける現象。 | ||
| 26 | フレーミング効果 | 同じことでも見方(フレーム)によって評価や判断が変わること。(水が半分もor半分しか) | ||
| 27 | プロスペクト理論 | 利得より損失の悲しみの方が大きく、損失局面ではリスク愛好的となる。 | ||
| 28 | おとり効果 | 追加の選択肢をあえて設定して元々あったものを選ばせる。(比較による認知) | ||
| 29 | アンカリング効果 | 最初の数値が無意識に基準となりその後の判断が非合理的にゆがむ。(定価取消し線) | ||
| 30 | 理由のパワー | 人にお願いするときに理由を添えるだけで受け入れられる可能性が上がる。 | ||
| 31 | 自立性バイアス | 自分の意志で決めたと思える要素があると主体性が生まれる。 | ||
| 32 | 感情 | アフェクトヒューリスティック | 喜怒哀楽よりもより淡い感情により非合理な意思決定(判断の簡易化)を行う。 | |
| 33 | 感情のマーカー | その人の過去の人生経験によりアフェクトが作られる。 | ||
| 34 | 拡張形成理論 | ポジティブな感情(アフェクト)が思考の幅を広めストレス耐性を強化する。 | ||
| 35 | 心理的所有感 | 自分のいるべき会社、仕事であると感じると自律的に熱心に働く。 | ||
| 36 | 保有効果 | 保有しているものに対して他人がつける価値よりもより価値があると思う傾向。 | ||
| 37 | 認知的再評価 | ネガティブな感情に目を向けて理解し再評価することでネガティブ感情を減少させる手法。 | ||
| 38 | すぐやめよう行動 | 目標を立てずにすぐにやめる前提で始める方がネガティブアフェクトが生れづらく始めやすい。 | ||
| 39 | キャッシュレス効果 | お金に対して保有効果を回避し利用額が上がる効果。”円”、”$”をつけない。 | ||
| 40 | 目標勾配効果 | ポイントカードなど目標に近づくにつれて行動や努力が加速する心理的な現象。 | ||
| 41 | コントロール感 | 人生をコントロールしたいという欲望。またコントロールできるものに依存する傾向。 | ||
| 42 | 境界効果 | コントロール感のない人に、囲いのあるパッケージ商品がコントロール感を与えられて売れた。 | ||
| 43 | 不確実性理論 | 先が読めないが史上最強のストレスである。 | ||
| 44 | メガミリオンズ効果 | 不確実性が極端に高いとポジティブなもの(宝くじ当選など)に導かれて不合理に判断。 | ||
行動経済学とは
経済活動における「人間の非合理な行動のメカニズムを解明する学問」です。
・これまでの経済学は利益追求の方向に常に合理的な判断をすることを前提としていた。
・そこに2002年頃、市場には「人々の心理状態」が影響するという発想が出現。
・そしてその人々の心理とは非常に非合理的であるという考えがミックスされた。
今ではアメリカを筆頭に世界的企業が市場戦略に行動経済学を取り入れている。
分類
行動経済学の歴史は浅く各理論の体系化が今まさに進んている状態。
現時点での分類(構成)は以下の通り。

※引用:「行動経済学が最強の学問である」著:相良奈美香
行動経済学をわかりやすく理解するおススメ!
初めて行動経済学に触れる人向けにわかりやすく解説してくれている本です。
具体例もあり、わかりやすくておススメです。✨
本書を読むことで「自分自身が非合理な生き物である」という点も客観的にとらえることもできると感じております。
内容を簡単に思い出したいときは是非↑のまとめ表をご活用ください。

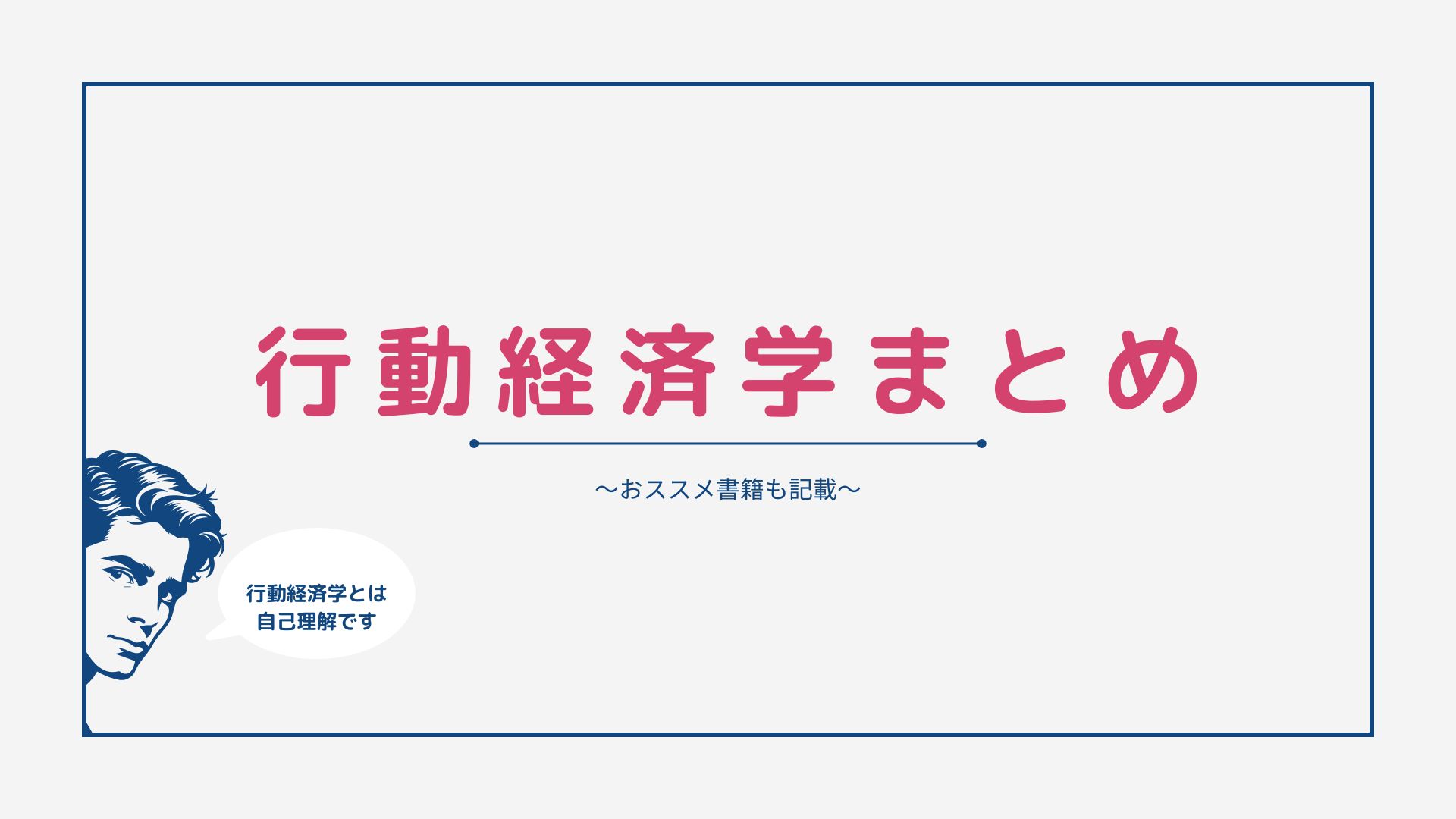
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d1b0dfc.e0816029.2d1b0dfd.8c26fa63/?me_id=1213310&item_id=20925080&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9503%2F9784815619503_1_5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント